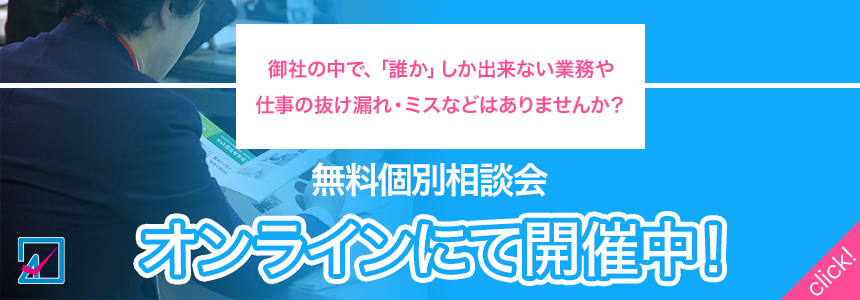【リモートワークでの活用】教育ツールとしてアニーを準備しておくことは今回非常にポイントになりました
会計事務所
セブンセンス税理士法人(セブンセンスグループ)
業種:税理士業

| 導入目的 | お客様ごとに手順の違う仕事内容等、従業員の教育ツール、個別の手順書・マニュアル作成 |
|---|---|
| 課題 | 教育に時間がかかること、担当の引き継ぎに時間がかかること(属人化しがち) |
| 効果 | 教育体制や仕事の手順が整い、リモートワーク(BPOセンターや在宅勤務)が実現できるように |
お客様ごとに違う、仕事手順の共有方法を探していました
(K:当社インタビュワー)
K:アニーを知ったきっかけは何だったのでしょうか?
雑誌のWedgeに掲載されていた広告を見て知りました。
私はもともと業務効率を上げるための仕組みや業務構築をしておりました。
以前から、私たちは分業という形で業務をみんなで分けて行っていたんです。
最初は、1人1人が全体を知っていたので上手くいってました。
しかし、新人が入ってくると、全体像を知らない状態で業務をさせなければならず
それでうまく行かない部分も出てきて、何とかしなければと思っていました。
業務が上手くいかなくなった要因は、「分業」のために業務を標準化しようと、すべてのお客様の業務を同じやり方にはめようとしていたからなのです。
しかしお客様ごとに個別の違う部分があり、同じやり方に当てはめるには無理がありました。
結局は担当者ベースのノウハウが必要になってしまっていたのです。
こういったお客様ごとに1件ずつ違うやり方を、どうやって共有しようかと思ってて、マニュアルシステムを探していました。
そのときにアニーと出会ったのです。
アニーの機能について詳しくはこちら
K:導入のときはいかがでしたか?
導入のタイミングは使い方のイメージはできてたんですが、全社に浸透するまでは1年かかりました。
初期設定はすぐ終わったんですが、社内的に使うまでに時間がかかりましたね。
個別にチェックリストを作らないといけないということで、1人1人に作成してもらうのが難しかったです。
そこで、ある程度業務が分かっていてコントロールできるような人に、チェックリスト作成を専任やってもらいました。
そして、500クライアント分の入力業務の手順書を作り上げました。
1年かけてチェックリスト作っては、お客様の業務をやってみて、というのを繰り返し、一通りやりました。
そしてチェックリストが準備された状態になってから、全社のメンバーに「使ってください」と広めていきました。
それと、チェックリストの加筆修正は、それぞれのスタッフがやっています。
立ち上げだけ、特定者で絞ってやったのが、上手く行った要因だと思います。
アニーを見て作業することが社内ルールに
K:アニーを使用してからはどのような変化がありましたか?
業務をするときに、チェックリストがなかったら「アニーがない」と言われることが増えました。
また当社では毎月違う人がお客様の業務をする体制なので、前任者がチェックリストのメンテナンスをしていないと突っ込まれるようになりました。
「チェックリストに載っていないといけない」という風土になり、アニーを見て作業をすることが会社にとって当たり前になってきました。
つまりアニーを使うことがルールになったんですよね。
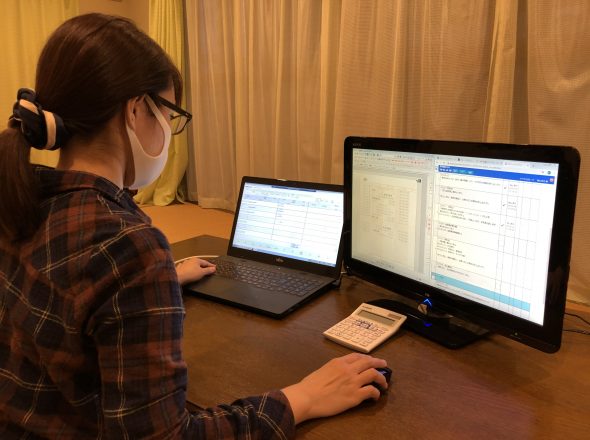
事情により従業員が家で仕事ができる措置も行えるように
K:テレワークでもご利用いただいているんですよね。
はい。感染症対策もあり、体調が少しすぐれない方や出社が難しい方がいらっしゃったら、家で仕事をしていただく措置も行えるようになっています。
今実際に取り入れているのは2,3名ぐらいですね。
法律上、事務所内でしなければならない業務もございますので、それ以外の業務でテレワークを活用しています。
ですので、単純なエントリー業務、領収書やレシートの入力、データの取り込み作業などの業務は在宅で行っていますね。
在宅で行う業務も、お客様ごとに作業内容が変わることがありますので、アニーが活用できています。
むしろ、アニーに手順書がなければ、お客様の作業の流れが分からないということになりますよね。
K:管理はどうしていますか?
普段から業務の割り振りをしている、クラウドツールの進捗管理表があるので、それを見ながら管理しています。
我々は仕事をお客様ではなく、工程ごとに貼り付けているんです。

担当を固定化せず、柔軟に回せるようになりました
K:沖縄県の石垣島にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)センターを持たれていると伺いました
はい。社内・社外の業務も含めBPOを行う拠点が石垣島にあります
この拠点は2015年ぐらいに設立しました。今は石垣島では社員・パートが15名ほど勤務しています。
資料の仕分けやデータのエントリー業務や、それらを給与明細に落とし込む仕事などをここで行っています。
ここでアニーを取り入れたのは2018年ぐらいです。
K:アニーを入れてどう変わりましたか?
昔は、作業するときは個人が自分専用の手順書を作って行っていましたが、アニーを導入してからはみんなが共通の物を使えるようになったことが、まず変わったところですね。
また、それまで、特にイレギュラーの案件は、1人ずつ教育しなければならなかったです。
その人が異動や退職となると、また同じ労力で教育しなければなりませんでした。
しかし、今はアニーがあるのでその引き継ぎがかなりスムーズになりましたね。
最初少しは研修するものの、アニー読んだらわかるようになってるからね、と指示できるようになりました。
また、業務に精通しているベテランさんが作ったマニュアルって、新人さんが見ても分からない部分が出てくるんです。
ですので、その箇所は新人さん自らに更新してもらうようにしています。
このように、アニーを使いながら育てていけるようになったのが大きいです。
マニュアルにはエクセルを昔使っていましたが、管理をする面ではアニーのほうがやりやすいですね。
メンテナンスのしやすさはアニーの方が断然、優位性があります。
作業を属人化させず、人を育てる点で、仕事がやりやすくなった実感があります。
アニーを活用して属人化を解消した事例はこちら
K:石垣島拠点のメンバーはクライアント担当を持っているのですか?
石垣の拠点では、固定の担当制はとっておらず、毎月担当を回しています。
業務量によって仕事に人を振り分けていますね。
また、途中で早退しないといけない事情があっても、別の人が引き継げるのが便利ですよね。
アニーを使ってくれてさえいれば、早退も受け入れやすいです。
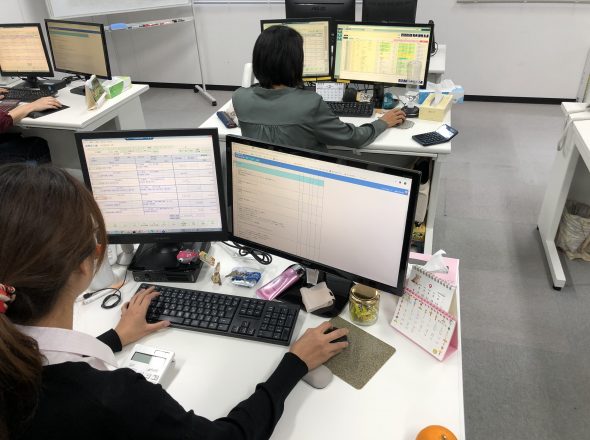
沖縄県と静岡県の遠距離でも管理が可能に
K:石垣島のBPOセンターの管理者は、どこにいるのですか?
静岡の拠点にいます。
K:石垣にいらっしゃらないんですね。
そうなんです。管理表でスケジュールと作業振り分けを見ています。
また定期的にアニーの使用状況を誰がどの案件で使っているか、というのをエクセルで見たりしています。
ベテランになると、「チェックリストなくてもできる」と、チェックリスト使われない方が出てきます。
しかし、そうするとメンテナンスされなくなってしまうので、ちゃんと使用しているか管理するようにしています。
アニーとはまとめてチェックするではなく、作業しながらチェックができるので
遠方地からでもどこまで進んでいるのかな?が見れるのが良いですよね。
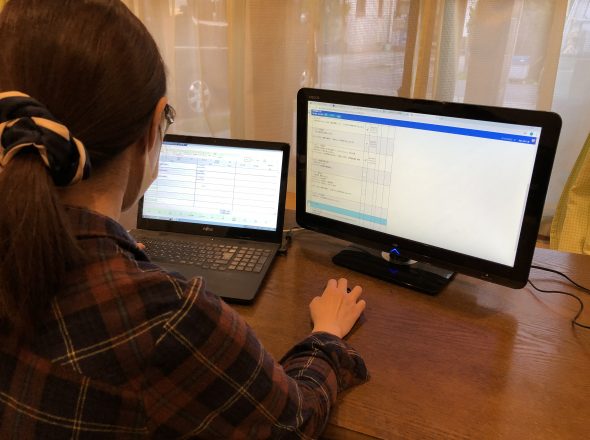
教育コストをいかに下げるか、というのが企業にとってポイントになるんです
K:在宅やリモートをでよかったことは?
時代のこともありますが、場所にとらわれずに仕事ができることは非常にありがたいですね。
例えば静岡拠点が止まってしまっても、他の拠点や自宅で仕事が継続できるなどリスクヘッジができますよね。
また、求人面でもメリットがあります。
東京などの大都市だと、なかなか求人が集まりませんが、地方だと集まりやすいパターンもあります。
ですので、地方にBPOセンターを置くと、雇用的な側面でも大都市に頼らなくても済むことは大きいですね。
しかしそうなると、遠隔地への指導や教育コストをいかに下げるか、というのが企業にとってポイントになるんです。
分かっている人は本社にいるけれど、遠隔地になかなか人を派遣はできないので。
ですので、こういった教育コストを下げるためにも、マニュアル・教育ツールとしてアニーを準備しておくことは今回非常にポイントになりましたね。
教育ができなければ、人が入ってきても即戦力にならないので
アニーを使えて良かったです。
K:ありがとうございました。今後ともアニーをご活用ください!